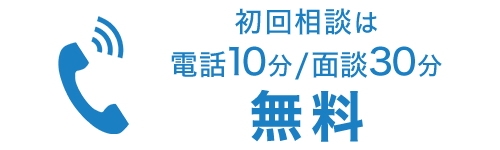2025.01.13 2025.01.13
専業主婦の財産分与ってどうなる? 離婚前に知っておくべき5つのポイント

「専業主婦の財産分与って、実際どうなるの?」
そんな疑問を抱えている方も多いのではないでしょうか。
毎日、家事に育児にと大忙し。
気づけば、自分のことは後回し…なんてこと、ありますよね。
離婚という二文字が頭をよぎったとき、まず気になるのがお金のこと。
特に専業主婦の方にとっては、離婚後の生活がどうなるのか、大きな不安を感じるかもしれません。
「共働きじゃないと、財産分与って不利になるのかな?」
「そもそも、どんな財産が対象になるの?」
この記事では、そんなあなたのモヤモヤを解消。
専業主婦の財産分与について、基本のキから、知っておくべきポイントまで、わかりやすく解説していきます。
目次
1. 財産分与の基本と専業主婦の立場
財産分与の法的根拠と種類
まず最初に、「財産分与」とは一体何か、その法的根拠から確認していきましょう。
実はこれ、日本の法律(民法)で認められた、夫婦が離婚する際に財産を分けるための制度なんです。
結婚生活中に夫婦で協力して築き上げた財産は、離婚時に公平に分けるのが基本。
この「公平に」というのがポイントで、専業主婦の方も、きちんと権利を主張できるんですよ。
財産分与には、大きく分けて3つの種類があります。
- 清算的財産分与:
夫婦が協力して築いた財産を、それぞれの貢献度に応じて分けるもの。
これが、財産分与の中心となる考え方です。 - 扶養的財産分与:
離婚後の生活に困窮する可能性がある場合に、経済的な支援として行われるもの。
特に、長年専業主婦だった方にとって、重要な要素となります。 - 慰謝料的財産分与:
離婚の原因を作った側が、相手に対して支払う慰謝料の一部として行われるもの。
不貞行為やDVなどが原因で離婚する場合に考慮されます。
これらのうち、特に重要なのが「清算的財産分与」。
専業主婦として家庭を支えてきたあなたの貢献は、経済的な価値として認められるべきなんです。
「でも、私は働いていないし…」
そう思われた方もいるかもしれませんね。
ご安心ください。
次の段落で、その理由を詳しく解説します。
専業主婦でも受け取れる理由
「専業主婦って、家で家事や育児をしているだけでしょ? それって、財産分与に関係あるの?」
そう思っている方もいるかもしれません。
確かに、毎月給料をもらっているわけではないので、不安になりますよね。
でも、ちょっと待ってください。
専業主婦の皆さんの、日々の家事や育児は、決して「タダ働き」ではありません。
家の中を綺麗に保ったり、美味しいご飯を作ったり、子どものお世話をしたり…
これらは全て、家庭を円満に保つために不可欠な、大切な「お仕事」なんです。
法律も、この点をちゃんと認めています。
夫婦が協力して築いた財産は、たとえ片方が専業主婦であっても、その貢献度に応じて公平に分けるべき、という考え方なんです。
これを「内助の功」といいます。
つまり、専業主婦の方は、家事や育児を通して、しっかりと財産形成に貢献しているとみなされるわけです。
例えるなら、会社の社長と社員の関係に似ています。
社長が会社を経営し、社員が業務をこなすように、夫婦もそれぞれの役割を担って家庭という「会社」を運営しているようなもの。
どちらが欠けても、円滑な運営は難しいですよね。
だから、共働きではないからといって、財産分与が少なくなるなんてことはありません。
安心して、自分の権利を主張してくださいね。
2. 離婚前に知っておくべき財産の整理ポイント
共有財産と特有財産の区別
さて、ここからは、実際に財産分与を行う際に、まず最初に押さえておくべきポイントを解説します。
それは、「共有財産」と「特有財産」の区別です。
「共有財産」とは、夫婦が結婚してから協力して築き上げてきた財産のことを指します。
具体的には、次のようなものが挙げられます。
- 預貯金:夫婦どちらかの名義であっても、結婚後に形成されたものは共有財産となります。
- 不動産:家や土地も、結婚後に購入したものであれば、共有財産となる可能性が高いです。
- 有価証券:株式や投資信託なども、結婚後の購入であれば共有財産です。
- 自動車:夫婦で共有して使っていた車も、財産分与の対象になります。
- 退職金:将来受け取る予定の退職金も、結婚期間中の分は財産分与の対象となる場合があります。
- 保険:解約返戻金のある保険も、共有財産として扱われることがあります。
一方で、「特有財産」とは、夫婦のどちらかが結婚前から持っていた財産や、結婚後でも個人的に相続や贈与で得た財産のことを指します。
こちらは、原則として財産分与の対象にはなりません。
例えば、結婚前に貯めていた預金や、親から相続した不動産などが「特有財産」にあたります。
ただし、特有財産であっても、夫婦の協力によって価値が維持・増加した場合には、一部が財産分与の対象となることもあります。
| 財産の種類 | 共有財産 | 特有財産 |
|---|---|---|
| 預貯金 | 結婚後に夫婦の協力で貯めたお金 | 結婚前から持っていたお金、相続や贈与で得たお金 |
| 不動産 | 結婚後に購入した家や土地 | 結婚前から持っていた家や土地、相続や贈与で得た不動産 |
| 有価証券 | 結婚後に購入した株式や投資信託 | 結婚前から持っていた株式や投資信託、相続や贈与で得た有価証券 |
| 自動車 | 結婚後に購入した車 | 結婚前から持っていた車、相続や贈与で得た車 |
| 退職金・年金 | 結婚期間中に積み立てられた部分 | 結婚前から積み立てられていた部分、相続や贈与で得た退職金や年金 |
| 保険 | 解約返戻金のある保険の結婚期間中の積み立て部分(保険の種類によって対象外となる場合もあり) | 結婚前から加入していた保険、相続や贈与で得た保険(解約返戻金がない掛け捨て型保険など) |
まずは、ご自身の財産を一つ一つ丁寧に洗い出し、どちらに該当するかを確認してみましょう。
通帳や契約書などを確認しながら、焦らず進めてくださいね。
財産状況を正確に把握する方法
次に、洗い出した財産を正確に把握する方法について解説します。
これが、財産分与をスムーズに進めるための重要なステップになります。
まずは、ご自身と配偶者の名義になっている財産を、可能な限り全てリストアップしましょう。
通帳、保険証券、不動産の登記簿謄本など、証拠となる書類をきちんと保管しておくことが大切です。
もし可能であれば、家計簿アプリやタブレットを活用するのもおすすめです。
最近では、銀行口座やクレジットカードと連携できる便利なアプリがたくさんあります。
これらを使えば、日々の入出金を自動的に記録できるので、財産状況を簡単に把握することができます。
タブレットなら、大きな画面で見やすいですし、写真やメモも一緒に残せるので便利ですよ。
特に、宮崎にお住まいの方は、地元で利用できるアプリやサービスなども活用してみるといいかもしれません。
また、もし配偶者が財産状況を開示してくれない場合は、弁護士に相談することも検討しましょう。
弁護士は、あなたの代わりに財産調査を行ったり、開示を求めることができます。
ご自身だけで悩まず、専門家の力を借りることも、時には必要です。
3. 財産分与の割合とトラブル回避策
一般的な割合と専業主婦への配慮
さて、財産を整理したところで、次に気になるのは「実際にどれくらい財産を分けられるのか?」という点ですよね。
一般的に、財産分与の割合は、夫婦それぞれが築き上げた財産に対する貢献度に応じて決定されます。
そして、その基本的な考え方は「2分の1ずつ」なんです。
「えっ、半分ももらえるの?」
そう思った方もいるかもしれませんね。
そうなんです!
専業主婦の方も、家事や育児を通して、夫婦の財産形成に貢献しているとみなされるため、原則として2分の1の割合で財産分与を受ける権利があります。
もちろん、これはあくまで原則です。
夫婦の状況によっては、この割合が調整されることもあります。
例えば、
- 夫婦の一方が、特別なスキルや才能によって、著しく財産形成に貢献した場合
- 夫婦の一方が、浪費やギャンブルによって、財産を大きく減らしてしまった場合
- 結婚期間が非常に短い場合
このようなケースでは、2分の1の割合から多少の増減が生じることもあります。
ですが、専業主婦の場合、多くは2分の1の割合が適用されると考えて良いでしょう。
長年、家庭を支え、家族のために尽くしてきたあなたには、それに見合うだけの権利があります。
自信を持って、自分の主張をしてくださいね。
交渉をスムーズに進めるコツ
財産分与の割合が分かったとしても、実際に夫婦で話し合うとなると、なかなかスムーズにいかないこともあります。
特に離婚となると、感情的になりがちですよね。
そこで、ここからは、少しでも円満に、かつスムーズに話し合いを進めるためのコツをお伝えします。
- 書面で合意内容を残す まずは、口約束ではなく、必ず書面で合意内容を残すようにしましょう。
後になって「言った」「言わない」の水掛け論になるのを防ぐことができます。
できれば、公正証書を作成するのがおすすめです。
公正証書は、公証役場で作成する公的な書類で、法的拘束力が高いのが特徴です。
もしもの時のために、作成しておくと安心です。 - 第三者(弁護士や調停委員)を頼る 夫婦だけで話し合いをすると、どうしても感情的になってしまい、冷静な話し合いが難しくなることがあります。
そんな時は、弁護士や調停委員といった第三者を頼ることも検討してみましょう。
特に、弁護士は法律の専門家なので、あなたの権利をしっかりと守ってくれます。
調停委員は、夫婦の間に立って、話し合いを円滑に進めるサポートをしてくれます。
お住まいの地域によっては、無料の法律相談窓口もあるので、一度相談してみるのも良いかもしれません。 - 冷静に、法律的な根拠に基づいて話し合う どうしても感情的になりやすい場面ですが、できるだけ冷静に、法律的な根拠に基づいて話し合うように心がけましょう。
感情論で話してしまうと、どうしても平行線になりがちです。
事前に財産を整理し、法律の専門家にも相談するなどして、根拠のある主張をするようにしましょう。
離婚は、人生における大きな転換期です。
少しでも後悔のない選択をするためにも、冷静に、そして慎重に進めていくことが大切です。
4. 離婚手続きの流れと必要な準備
協議離婚から調停・裁判までのステップ
さて、財産分与について理解を深めたところで、ここからは離婚の手続きについて見ていきましょう。
離婚の手続きには、大きく分けて以下の4つのステップがあります。
1.協議離婚
まずは、夫婦間で話し合いを行い、離婚について合意を目指します。離婚の条件(財産分与、慰謝料、養育費など)についても、この段階で話し合います。もし、夫婦間で合意ができれば、離婚届を提出し、離婚が成立します。これが、一番スムーズな離婚の形です。
2.離婚調停
夫婦間での話し合いがうまくいかない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てることができます。調停では、調停委員が間に入り、夫婦双方の意見を聞きながら、合意を目指します。調停はあくまでも話し合いの場であり、裁判のように強制力はありません。
3.離婚審判
調停でも合意に至らない場合は、裁判官が審判を下すことがあります。審判は、裁判のような判決ではなく、裁判官が双方の主張や証拠を考慮して、妥当な解決策を示すものです。審判の結果に不服がある場合は、異議申し立てを行うことも可能です。
4.離婚裁判
調停や審判でも解決できない場合は、最終的に裁判で離婚の可否や条件を決めることになります。裁判では、双方の主張や証拠を基に、裁判官が判決を下します。裁判は、時間も費用もかかるため、できる限り避けたいところです。
財産分与については、どのステップにおいても話し合うことができますが、特に協議離婚の段階でしっかりと話し合っておくことが大切です。調停や裁判に進むと、時間も費用もかかってしまうため、まずは夫婦でよく話し合うことを心がけましょう。
必要書類と相談先の選び方
離婚の手続きを進めるにあたって、事前に準備しておくべき書類がいくつかあります。
また、相談する相手によって、手続きを進める上での注意点も変わってきます。
まずは、必要な書類について確認していきましょう。
- 戸籍謄本:離婚する夫婦の戸籍が記載されている書類です。本籍地の役所で取得することができます。
- 住民票:夫婦の住所が記載されている書類です。住民登録をしている役所で取得できます。
- 財産関係の書類:預貯金通帳、不動産の登記簿謄本、保険証券など、財産分与に関する書類です。できる限り、全ての財産がわかるように準備しましょう。
- 年金分割のための情報通知書:年金分割を希望する場合は、年金事務所で取得する必要があります。
- 印鑑:離婚届やその他の書類に押印するために必要です。
これらの書類を事前に準備しておくことで、手続きをスムーズに進めることができます。
次に、離婚に関する相談ができる主な窓口と、それぞれの特徴をまとめました。
ご自身の状況やニーズに合わせて、適切な相談先を選んでみましょう。
| 相談先 | 専門分野 | メリット | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 弁護士 | 法律全般 | 法律の専門家として、交渉や裁判を代理してくれる。複雑な法律問題を解決できる。 | 費用が高くなる傾向がある。 |
| 司法書士 | 書類作成、不動産登記など | 離婚協議書や公正証書作成をサポートしてくれる。不動産登記手続きにも詳しい。 | 交渉は弁護士の専門分野。 |
| 行政書士 | 書類作成 | 比較的費用を抑えて、離婚協議書などの書類作成を依頼できる。 | 交渉はできない。複雑な法律問題には対応できない場合がある。 |
| 法テラス | 法律相談、弁護士紹介 | 経済的に余裕がない場合でも、弁護士を紹介してくれたり、無料相談を利用できる。 | 相談できる時間や回数が限られる場合がある。 |
| 自治体の相談窓口 | 離婚に関する一般的な相談 | 無料で相談できることが多い。地域の情報に詳しい。 | 法律的なアドバイスや具体的な解決策を求める場合は、弁護士など専門家への相談が必要になる。 |
相談先を選ぶ際には、それぞれの専門分野や費用、相性などを考慮して、自分に合ったところを選ぶようにしましょう。
特に、離婚はデリケートな問題なので、信頼できる相手を選ぶことが重要です。
5. スムーズな財産分与を実現するために
書面での合意と弁護士への相談
さて、ここまで財産分与の基本から離婚手続きまで、様々なポイントを見てきました。
最後に、これまでの情報を踏まえ、スムーズな財産分与を実現するために、さらに重要なポイントを2つお伝えします。
まず1つ目は、「書面での合意」です。
離婚の話し合いがまとまったら、必ずその内容を書面に残しましょう。
口約束だけでは、後になって「言った」「言わない」のトラブルになりかねません。
合意した内容を明確にするためにも、書面での合意は必須です。
書面には、以下の内容を記載するようにしましょう。
- 離婚の合意
- 財産分与の内容(金額、対象となる財産、支払い方法など)
- 慰謝料、養育費、年金分割の有無と内容
- その他、合意した事項
この書面は、夫婦で作成することもできますが、より確実なものにするためには、弁護士や司法書士に依頼して作成してもらうのがおすすめです。
特に、公正証書として作成すれば、法的拘束力も高まり、後々のトラブルを防ぐことができます。
公正証書は、公証役場で作成してもらうことができ、費用はかかりますが、それ以上の安心感を得られるでしょう。
そして、2つ目は、「早めに専門家(弁護士)への相談」です。
離婚は、法的な手続きが複雑であり、感情的な対立も生じやすい問題です。
そのため、できるだけ早い段階で、弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、以下のようなメリットが得られます。
- 法律の専門家として、あなたの権利をしっかりと守ってくれる
- 財産分与や慰謝料などの金額について、適正なアドバイスをもらえる
- 相手との交渉を代わりに行ってくれる
- 離婚協議書や公正証書の作成をサポートしてくれる
- 調停や裁判になった場合にも、代理人として対応してくれる
弁護士費用はかかりますが、それ以上の安心感と、スムーズな解決につながる可能性が高くなります。
特に、財産分与の金額が大きい場合や、相手との関係がこじれている場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
宮崎にお住まいの方であれば、地元に詳しい弁護士を探してみるのも良いでしょう。
離婚後の生活設計と今からできる対策
財産分与が終われば、いよいよ離婚後の生活がスタートします。
離婚後の生活をスムーズに進めるためには、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。
まずは、離婚後の生活設計を立ててみましょう。
具体的には、以下のような点を考慮して計画を立ててみてください。
- 収入源の確保:離婚後の生活費をどうするか、具体的な計画を立てましょう。
仕事を探す、スキルアップのための勉強をするなど、収入源を確保するための行動が必要です。 - 住まいの確保:離婚後、どこに住むのかを決めましょう。
実家に戻る、新しい住まいを探すなど、状況に応じて適切な選択が必要です。 - 子育ての準備:お子さんがいる場合は、養育費の取り決めや、学校の手続き、お子さんの心のケアなど、子育てに関する準備も必要です。
- 公的支援制度の利用:国や自治体では、離婚後の生活を支援するための様々な制度があります。
例えば、児童扶養手当やひとり親家庭への支援制度など、利用できる制度がないか確認してみましょう。
宮崎県や宮崎市でも、様々な支援制度がありますので、お住まいの地域の情報を調べてみてください。 - 情報収集:インターネットやSNSを活用して、離婚に関する情報を集めましょう。
同じような経験をした人のブログや、専門家のコラムなど、参考になる情報がたくさんあります。
情報収集をすることで、不安を軽減したり、新たな発見があるかもしれません。
離婚後の生活は、不安なことも多いかもしれませんが、しっかりと準備しておけば、必ず乗り越えられます。
まずは、一歩ずつ、できることから始めてみましょう。
そして、もし困ったことがあれば、遠慮せずに専門家や公的機関に相談してくださいね。
まとめ
今回の記事では、専業主婦の財産分与について、基本的なことから、具体的な注意点まで、幅広く解説してきました。
覚えておいていただきたいのは、専業主婦の方も、家事や育児を通して、夫婦の財産形成に十分に貢献しているということです。
決して、「自分には権利がない」などと思わないでください。
結婚生活の中で築き上げた財産の半分は、あなたにも正当な権利があるのです。
もし、離婚を考えているのであれば、まずは落ち着いて、ご自身の財産を整理してみましょう。
そして、今回お伝えしたポイントを踏まえ、しっかりと話し合いを進めてください。
話し合いがうまくいかない場合は、早めに弁護士などの専門家に相談することも検討しましょう。
離婚は、人生における大きな転換期です。
不安や迷いを感じることもあるかと思いますが、決して一人で抱え込まないでください。
周りの人に相談したり、専門家の力を借りながら、一歩ずつ、前に進んでいきましょう。
そして、何よりも大切なのは、「自分が納得できる形で、新たな一歩を踏み出す」ということです。
今回の記事が、そのための少しでもお役に立てれば幸いです。
このコラムの監修者

岩澤法律事務所
岩澤 千洋弁護士宮崎県弁護士会所属
日々の生活で生じる悩みの多くは法的な問題に分析することができ、何かしらの法的な解決(目的地)を見つけることができます。まずは、お気軽にご相談ください。どのような問題であれ、何事も依頼者の方の立場利益を第一に考えて、できる限り依頼者の方の利益にかなう解決(目的地)に向けて最善の努力をいたします。