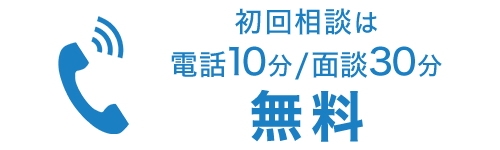2025.04.23 2025.04.23
離婚の手続きを徹底解説!初めての方でもわかる流れとポイント

離婚を考え始めたとき、多くの方が「どこから手をつければいいのか」「どんな手続きが必要なのか」と不安を感じるものです。
特に初めての方にとっては、法律用語や複雑な手続きが壁となり、一歩を踏み出せないこともあるでしょう。
この記事では、離婚手続きの基本的な流れから必要な書類、そして離婚後の手続きまで、初めての方にもわかりやすく解説します。
これから離婚を考えている方はもちろん、すでに進行中の方にとっても参考になる情報をまとめました。
目次
はじめに:離婚を考えたときの最初の一歩
離婚は人生の大きな転機です。感情的になりがちですが、冷静に対応することが重要です。
まずは深呼吸をして、これからの道のりを整理してみましょう。
離婚を考え始めたときの心構え
離婚を考え始めたとき、まず大切なのは「感情」と「現実的な判断」を分けて考えることです。
怒りや悲しみといった感情は自然なものですが、それらに流されず、将来の生活や子どもの福祉を第一に考えた冷静な判断が必要です。
また、離婚は法律的な手続きだけでなく、精神的・経済的な準備も必要です。
信頼できる人に相談したり、専門家のアドバイスを受けたりすることで、不安を軽減できるでしょう。
ポイント
- 感情に流されず、冷静に判断しましょう
- 将来の生活設計を考えておきましょう
- 必要に応じて専門家に相談しましょう
離婚前に確認しておくべきこと
離婚を決断する前に、以下のポイントを確認しておくと良いでしょう。
- 離婚の理由と目的の明確化:
なぜ離婚したいのか、離婚後どのような生活を望むのかを整理する - 財産状況の把握:
夫婦の財産(不動産、預貯金、ローンなど)を把握する - 子どもへの影響の検討:
子どもがいる場合、親権や養育費、面会交流について考える - 離婚後の生活設計:
住居、収入、支出などの生活基盤を検討する
これらを事前に整理しておくことで、離婚協議や手続きがスムーズに進みやすくなります。
離婚手続きの種類と選び方
日本の法律では、離婚の方法は主に4種類あります。
それぞれの特徴を理解し、自分の状況に合った方法を選びましょう。
協議離婚:話し合いで進める最も一般的な方法
協議離婚は、夫婦間の話し合いで離婚条件について合意し、離婚届を提出する方法です。
日本の離婚の約90%がこの方法で行われています。
特徴
- 手続きが簡単で費用がほとんどかからない
- 短期間で離婚が成立する(合意さえできれば即日も可能)
- 裁判所を介さないため、プライバシーが守られる
ただし、離婚条件について十分な取り決めがなされないまま離婚してしまうリスクもあります。
特に子どもがいる場合や財産が多い場合は、しっかりと話し合いをしておくことが重要です。
調停離婚:第三者を交えて解決を目指す
協議離婚では話がまとまらない、あるいは夫婦の一方が離婚に応じてくれない場合に行う方法です。
家庭裁判所の調停委員という第三者を交えて話し合いを進めます。
特徴
- 第三者が間に入るため、冷静な話し合いが可能
- 法的知識を持つ専門家のアドバイスが得られる
- 調停調書には執行力があり、取り決めが守られない場合に強制執行が可能
調停は平均4〜6ヶ月程度かかり、複数回の調停期日に出席する必要があります。
裁判離婚:最終手段としての選択肢
調停でも合意に達せず、かつ法律で定められた離婚事由がある場合に行う方法です。
裁判所の判決によって離婚が成立します。
特徴
- 相手が離婚に応じなくても離婚が可能
- 判決には執行力があり、取り決めが守られない場合に強制執行が可能
- 時間と費用がかかる(1〜2年程度、弁護士費用を含めると数十万円〜)
裁判離婚では、民法第770条に定められた離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、配偶者の重度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由)のいずれかが必要です。
あなたに合った離婚方法の選び方
どの離婚方法を選ぶかは、以下のポイントを考慮して決めましょう。
| 状況 | おすすめの方法 |
|---|---|
| 夫婦間で話し合いができる | 協議離婚 |
| 話し合いが難しいが、離婚自体には双方が同意 | 調停離婚 |
| 相手が離婚に応じない | 調停離婚→裁判離婚 |
| DVや虐待がある | 弁護士に相談の上、調停または裁判離婚 |
どの方法を選ぶにしても、専門家に相談することで、より適切な判断ができるでしょう。
協議離婚の流れとポイント
協議離婚は最も一般的な離婚方法です。手続きの流れとポイントを押さえておきましょう。
協議離婚のメリット・デメリット
メリット
- 手続きが簡単で費用がほとんどかからない
- 短期間で離婚が成立する
- 裁判所を介さないため、プライバシーが守られる
- 夫婦の合意に基づくため、感情的な対立が少ない
デメリット
- 離婚条件について十分な取り決めがなされないリスクがある
- 法的知識がないと不利な条件で合意してしまう可能性がある
- 口約束だけでは後から条件が守られない可能性がある
- 一方が離婚に応じない場合は成立しない
話し合いを円滑に進めるコツ
協議離婚では、夫婦間の話し合いが重要です。
以下のポイントを意識すると、話し合いがスムーズに進みやすくなります。
1. 感情的にならず、冷静に対応する
- 過去の出来事を蒸し返さない
- 相手を責めるのではなく、解決策を考える姿勢で臨む
2. 話し合いの場所と時間を適切に選ぶ
- 落ち着いて話せる場所を選ぶ
- 十分な時間を確保する
- 必要に応じて第三者(弁護士など)の同席を検討する
3. 話し合うべき事項を明確にする
- 親権、養育費、面会交流
- 財産分与、慰謝料
- 住居、ローンの取り扱い
- 姓の選択
4. メモを取りながら進める
- 合意した内容を書き留めておく
- 後日の確認のために日付も記録しておく
離婚協議書の重要性と作成のポイント
離婚協議書は法的には必須ではありませんが、作成を強く推奨します。口約束だけでは後から「言った・言わない」のトラブルになりかねません。
離婚協議書に記載すべき内容
- 基本情報(夫婦の氏名、生年月日、住所、婚姻年月日、離婚合意日)
- 親権・監護権の取り決め
- 養育費(金額、支払期間、支払方法、支払日、不払い時の対応)
- 面会交流(頻度、方法、場所、費用負担)
- 財産分与(不動産、預貯金、株式・投資信託、自動車などの動産、ローン・借金の分担)
- 慰謝料(金額、支払方法)
- その他の取り決め(婚姻費用の清算、氏の使用など)
離婚協議書は公正証書にすることで、強制執行力を持たせることができます。
特に養育費の支払いなど、長期間にわたる約束については、公正証書にしておくことをお勧めします。
公正証書のメリット
- 強制執行力がある(約束が守られない場合に強制執行が可能)
- 証拠としての価値が高い
- 内容の正確性が担保される
離婚届の書き方と提出方法
離婚届は市区町村役場で入手するか、各自治体のウェブサイトからダウンロードすることができます。
離婚届の記入ポイント
- 夫婦双方の署名・捺印
- 成人の証人2名の署名・捺印
- 未成年の子どもがいる場合は親権者の記入
- 氏の選択(結婚時に姓を変えた方が元の姓に戻るかどうか)
離婚届の提出に必要なもの
- 離婚届(必要事項を記入したもの)
- 本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
- 戸籍謄本(本籍地以外の役所に提出する場合)
離婚届は本籍地または住所地の市区町村役場に提出します。
夫婦のどちらか一方が提出しても受理されますが、できれば二人で行くことをお勧めします。
調停離婚・裁判離婚の基礎知識
協議離婚で合意に至らない場合は、調停離婚や裁判離婚という選択肢があります。
調停離婚の申立て方法と流れ
調停離婚は、家庭裁判所に「夫婦関係調停申立書」を提出することで始まります。
申立てに必要な書類
- 夫婦関係調停申立書
- 戸籍謄本(申立日前3ヶ月以内に発行されたもの)
- 申立人の住民票
- 収入印紙(1,200円分)
- 連絡用の郵便切手(裁判所によって金額が異なる)
申立ては相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に行います。
申立てから約1ヶ月後に第1回調停期日が設定され、その後複数回の調停を重ねていきます。
調停の流れ
- 申立て
- 第1回調停期日の通知
- 調停の実施(当事者双方から個別に事情を聴取)
- 複数回の調停を重ねて条件を詰めていく
- 合意に達した場合:調停調書が作成され、離婚が成立
- 合意に達しない場合:調停不成立となり、審判または訴訟へ移行することも可能
調停で合意を得るためのポイント
調停を有利に進めるためには、以下のポイントに注意しましょう。
1. 事前準備を十分に行う
- 主張したい内容を整理する
- 必要な証拠を収集する
- 希望する条件を明確にする
2. 感情的にならず冷静に対応する
- 調停委員に好印象を与える
- 相手の挑発に乗らない
3. 現実的な要求をする
- 法律や判例に基づいた妥当な要求をする
- 譲歩できる点は柔軟に対応する
4. 子どもがいる場合は子どもの利益を最優先する
- 親権や面会交流について子どもの福祉を考慮した提案をする
裁判離婚が必要になるケース
以下のようなケースでは、裁判離婚が必要になることがあります。
- 調停でも合意に達しない場合
- 相手が調停に応じない場合
- 明確な離婚事由がある場合(不貞行為、DV、悪意の遺棄など)
裁判離婚では、民法第770条に定められた離婚事由のいずれかを証明する必要があります。
特に「その他婚姻を継続し難い重大な事由」は幅広く解釈されますが、証拠の提示が重要です。
裁判離婚の流れ
- 訴状の提出
- 訴状の送達
- 口頭弁論
- 証拠調べ
- 和解勧告
- 判決
- 離婚届の提出
裁判離婚は平均1〜2年程度かかり、弁護士費用を含めると数十万円以上の費用がかかることもあります。
弁護士に依頼するメリット
離婚手続き、特に調停や裁判では、弁護士に依頼することで多くのメリットがあります。
- 法的知識に基づいた適切なアドバイスが受けられる
- 感情的になりがちな交渉を冷静に進められる
- 必要な証拠の収集や書類の作成をサポートしてもらえる
- 相手方との直接のやり取りを避けられる
- 有利な条件での合意を目指せる
特に以下のようなケースでは、弁護士への相談を強くお勧めします。
- DVや虐待がある場合
- 財産が複雑な場合(不動産、事業、海外資産など)
- 子どもの親権や養育費で揉めている場合
- 相手が離婚に応じない場合
- 国際結婚の離婚の場合
離婚時に決めておくべき重要事項
離婚時には、以下の重要事項について取り決めておく必要があります。
親権と養育費:子どもの将来のために
親権とは
親権とは、未成年の子どもの監護・教育・財産管理などを行う法的な権利と義務です。
日本では離婚後の共同親権は認められておらず、どちらか一方が親権者となります。
親権者の決定基準
- 子どもの福祉・利益を最優先
- 子どもの年齢・意思
- 監護能力(経済力、生活環境、時間的余裕など)
- これまでの監護状況
- 父母の協力関係
養育費について
養育費は、親権者とならなかった親が子どもの成長のために支払う費用です。
養育費の算定方法
- 裁判所の算定表を参考に算出
- 双方の収入、子どもの人数・年齢を考慮
- 特別な事情(病気、障害など)がある場合は調整
養育費の相場(月額)
- 子ども1人の場合:3〜5万円
- 子ども2人の場合:5〜8万円
- 子ども3人の場合:7〜10万円
ただし、これはあくまで目安であり、個々の事情によって異なります。
財産分与:共有財産の分け方
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して形成した財産を公平に分配する制度です。
財産分与の対象となるもの
- 不動産(住宅、土地など)
- 預貯金、現金
- 株式、投資信託、保険の解約返戻金
- 自動車、家具、家電などの動産
- 退職金(既に受け取ったものや受給権が確定しているもの)
財産分与の対象とならないもの
- 婚姻前から所有していた財産
- 婚姻中に相続・贈与で取得した財産
- 個人的な使用物(衣類、装飾品など)
財産分与の計算方法
- 婚姻中に形成した財産を洗い出す
- それぞれの財産の評価額を算定する
- 夫婦の貢献度を考慮して分配割合を決定(原則は50:50)
- 具体的な分与方法を決定(現物分与、代償分与、換価分与)
慰謝料:請求できるケースと相場
慰謝料は、離婚の原因を作った配偶者に対して請求できる精神的苦痛に対する賠償金です。
慰謝料が認められる主な事由
- 不貞行為(浮気・不倫)
- DV(身体的・精神的暴力)
- 悪意の遺棄
- アルコール・薬物依存
- ギャンブル依存
慰謝料の相場
- 不貞行為:100万円〜300万円
- DV:50万円〜500万円
- 悪意の遺棄:50万円〜200万円
ただし、これはあくまで目安であり、個々の事情によって大きく異なります。
面会交流:子どもと非監護親の関係維持
面会交流は、離婚後に親権者とならなかった親が子どもと定期的に会って交流する権利です。
面会交流の方法
- 直接会う(自宅、公共施設、レジャー施設など)
- 宿泊を伴う交流
- 電話・手紙・メール・ビデオ通話などでの交流
面会交流の頻度
- 月1〜2回が一般的
- 子どもの年齢や生活状況に応じて調整
- 長期休暇(夏休み、冬休みなど)の利用
面会交流の取り決め事項
- 頻度・時間
- 場所・方法
- 引き渡し方法
- 費用負担
- キャンセル時の対応
面会交流は子どもの健全な成長のために重要ですが、DVや虐待の履歴がある場合など、子どもの福祉に反する場合は制限されることもあります。
離婚後に必要な手続きチェックリスト
離婚が成立したら、新しい生活のスタートに向けて様々な手続きが必要です。
これらを忘れると後々トラブルになることもあるため、計画的に進めていきましょう。
戸籍・住民票関連の手続き
離婚後まず最初に取り組むべきなのが、身分関係の基本的な手続きです。
戸籍の変更
- 離婚届の提出により自動的に処理されます
- その後の手続きのために戸籍謄本を数通取得しておくと便利です
住民票の変更
- 住所変更がある場合は転出・転入届を提出します
- 世帯構成が変わるため、世帯分離・世帯合併の手続きも必要です
- これらは新居の住所地の市区町村窓口で行います
氏の変更
- 結婚時に姓を変えた方は、元の姓に戻るか選択できます
- 離婚届提出時に記入します
- 離婚から3ヶ月以内なら届出だけで可能ですが、それ以降は家庭裁判所の許可が必要です
実践アドバイス
戸籍・住民票関連の手続きは早めに済ませましょう。
特に氏の変更は期限があるため注意が必要です。
健康保険・年金の切り替え
離婚により扶養関係が変わると、健康保険や年金の加入状況も変更する必要があります。
健康保険の切り替え
- 被扶養者だった場合は国民健康保険に新たに加入します
- 自分が勤務先の健康保険に加入している場合は、元配偶者を被扶養者から外す手続きが必要です
- 国民健康保険の加入手続きは住所地の市区町村窓口で行います
国民年金の加入手続き
- 第3号被保険者(配偶者の扶養)だった方は、第1号被保険者への切り替えが必要です
- 市区町村の国民年金窓口で手続きします
年金分割の請求
- 婚姻期間中の厚生年金保険料の納付実績を分割できる制度です
- 特に専業主婦(夫)だった方は将来の年金額に大きく影響します
- 離婚から2年以内に年金事務所で手続きする必要があるため、期限に注意しましょう
子どもに関する手続き
子どもがいる場合は、子どもに関連する手続きも漏れなく行うことが重要です。
児童手当・児童扶養手当の申請
- 親権者が市区町村の窓口で手続きします
- これまで配偶者が受給していた場合は受給者変更の手続きが必要です
- ひとり親家庭となる場合は児童扶養手当の申請も可能です
- これらの手当は家計の支えとなるため、早めに手続きしましょう
学校・保育園への届出
- 氏名変更や緊急連絡先変更の届出を行います
- 住所が変わる場合は転校手続きも必要です
- 学校や保育園の先生には家庭環境の変化について適切に伝えておくと良いでしょう
子どもの健康保険の切り替え
- 親権者の健康保険に加入する手続きを行います
- 医療費の助成制度なども確認しておきましょう
その他の生活関連手続き
日常生活に関わる様々な手続きも、優先順位をつけて進めていきましょう。
各種証明書・カード類の変更
- マイナンバーカード・通知カードの変更
- 運転免許証の変更
- パスポートの変更
- クレジットカードの変更
- 銀行口座の変更
氏が変わる場合は特に重要です。身分証明書は優先的に変更しましょう。
住居・公共料金の名義変更
- 賃貸契約の名義変更
- 電気・ガス・水道の名義変更
- インターネット・携帯電話の契約変更
住居環境が変わる場合は、これらの手続きも計画的に進めることが大切です。
保険の見直し
- 生命保険の受取人変更
- 医療保険・がん保険などの見直し
特に元配偶者が受取人になっている場合は、早急に変更することをお勧めします。
離婚後の手続きは多岐にわたりますが、一つひとつ確実に進めることで、新しい生活の基盤を固めることができます。
不明点があれば、各窓口で相談するか、専門家のアドバイスを受けることをお勧めします。
よくある質問と回答
離婚に関してよくある質問とその回答をまとめました。
離婚にかかる費用について
Q: 離婚にはどのくらいの費用がかかりますか?
A: 離婚方法によって費用は大きく異なります。
- 協議離婚:
離婚届の提出のみなので基本的に費用はかかりません。ただし、離婚協議書を公正証書にする場合は1〜5万円程度の費用がかかります。 - 調停離婚:
申立手数料(1,200円)と切手代(800円程度)がかかります。弁護士に依頼する場合は別途弁護士費用(20〜50万円程度)が発生します。 - 裁判離婚:
訴訟費用(13,000円〜)に加え、弁護士費用(30〜100万円程度)がかかります。
離婚までの期間について
Q: 離婚までどのくらいの期間がかかりますか?
A: 離婚方法によって期間は異なります。
- 協議離婚:
最短即日(離婚届を提出した日に成立)。一般的には1〜3ヶ月程度(離婚条件の協議に要する期間)。 - 調停離婚:
平均4〜6ヶ月。複雑な案件では1年以上かかることも。 - 裁判離婚:
平均1〜2年。複雑な案件や控訴された場合はさらに長期化。
相手が離婚に応じない場合の対処法
Q: 相手が離婚に応じない場合はどうすればよいですか?
A: 相手が離婚に応じない場合は、以下の手順で進めることができます。
- まずは冷静に話し合いを試みる
- 話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に調停を申し立てる
- 調停でも合意に至らない場合は、離婚事由があれば裁判で離婚を請求する
裁判では、民法第770条に定められた離婚事由(不貞行為、悪意の遺棄、3年以上の生死不明、配偶者の重度の精神病、その他婚姻を継続し難い重大な事由)のいずれかを証明する必要があります。
養育費が支払われない場合の対応
Q: 養育費が支払われない場合はどうすればよいですか?
A: 養育費が支払われない場合は、以下の対応が可能です。
- 話し合いによる解決:
まずは相手に支払いを求める - 家庭裁判所の履行勧告・履行命令:
家庭裁判所に申し立てて、相手に支払いを促してもらう - 強制執行:
公正証書や調停調書、判決があれば、給与差押えなどの強制執行が可能 - 養育費立替払制度の利用:
一部の自治体では、養育費が支払われない場合に立替払いを行う制度がある
養育費の取り決めは、できるだけ公正証書にしておくことをお勧めします。
まとめ:新しい人生のスタートに向けて
離婚は人生の大きな転機ですが、適切な準備と手続きを行うことで、新しい人生のスタートをスムーズに切ることができます。
離婚手続きの重要ポイント再確認
- 離婚方法を適切に選ぶ:
協議離婚、調停離婚、裁判離婚のいずれかを状況に応じて選択 - 離婚条件をしっかり決める:
親権、養育費、面会交流、財産分与、慰謝料などを明確に - 離婚協議書を作成する:
口約束だけでなく書面に残し、できれば公正証書にする - 離婚後の手続きを忘れずに:
戸籍・住民票、健康保険・年金、子どもに関する手続きなど
専門家に相談することの大切さ
離婚手続きは複雑で専門的な知識が必要な場合も多いため、不安や疑問がある場合は早めに専門家に相談することをお勧めします。
特に以下のようなケースでは、専門家の助けが有効です。
- DV・モラハラなどの被害がある場合
- 財産が複雑な場合(不動産、事業、海外資産など)
- 子どもの親権や養育費で揉めている場合
- 相手が離婚に応じない場合
- 国際結婚の離婚の場合
岩澤法律事務所のサポート
岩澤法律事務所では、離婚問題に関する無料相談も実施しています。
経験豊富な弁護士が、あなたの状況に合わせた適切なアドバイスを提供します。
離婚は終わりではなく、新しい人生の始まりです。
この記事が、離婚を考えている方の一助となれば幸いです。不安なことがあれば、ぜひ専門家に相談してください。
岩澤法律事務所 離婚相談窓口
- 電話:0985-77-8177(平日/土日祝 9:00〜22:00)
- 初回相談無料
このコラムの監修者

岩澤法律事務所
岩澤 千洋弁護士宮崎県弁護士会所属
日々の生活で生じる悩みの多くは法的な問題に分析することができ、何かしらの法的な解決(目的地)を見つけることができます。まずは、お気軽にご相談ください。どのような問題であれ、何事も依頼者の方の立場利益を第一に考えて、できる限り依頼者の方の利益にかなう解決(目的地)に向けて最善の努力をいたします。